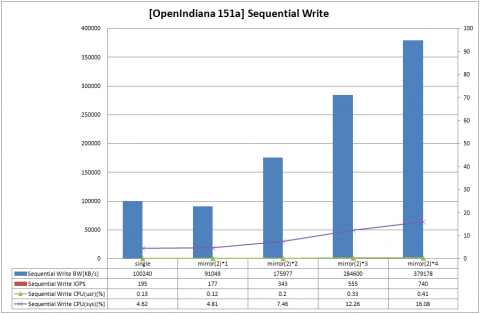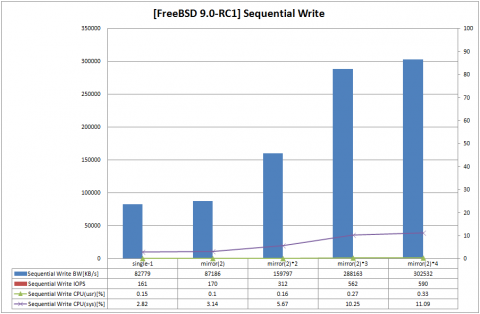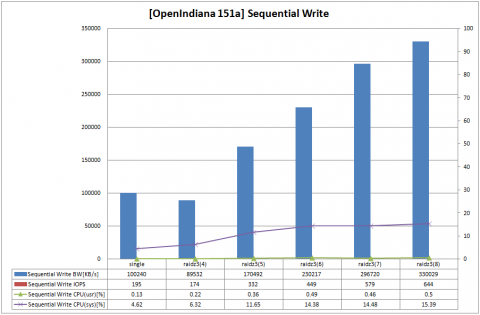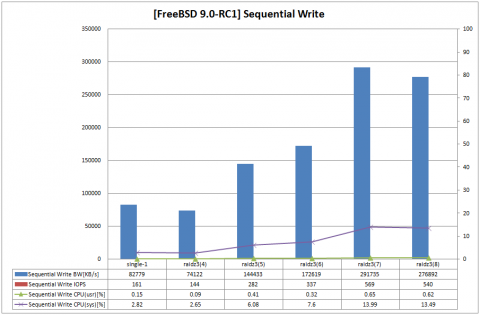STMF(COMSTAR)からFile(NFS)への移行調査 - zvol to file編
Posted on 2016/03/06(Sun) 01:20 in technical • Tagged with COMSTAR, iscsi, openindiana, ZFS
OpenIndiana + ZFS + COMSTARなiSCSIから、Proxmox VE + NFSな環境に移行する場合の話。
zvolのmetaデータを外出しにしているので、zvolをddしてrawデータを抽出するだけで済むはず。
通報
OpenIndianaのiSCSI(STMF)の場合、LU作成時にメタデータが付与されるので、そのままでは移行しにくくなることが予想されます。
メタデータを外部ファイ …
Continue reading